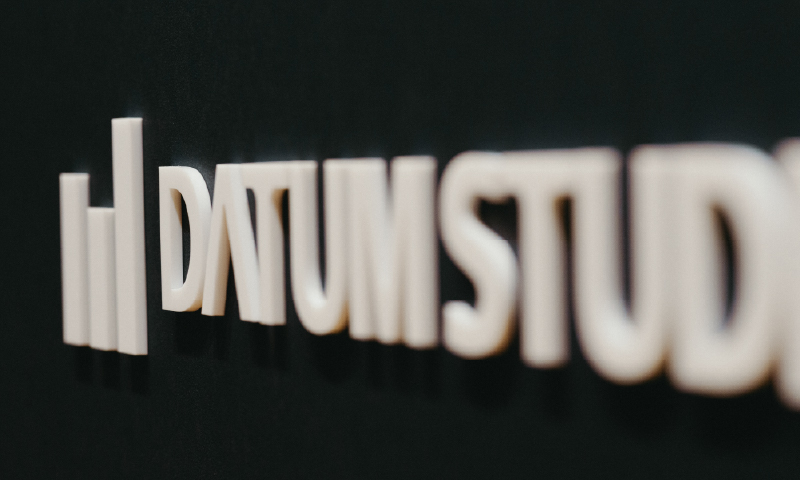magazine
ヒト・コトを知る
経験を力に変え、持続可能な成長を
データで社会を動かすエンジニアの挑戦
カスタマーアナリティクス部 データエンジニア
2021年、DATUM STUDIOに新卒入社。入社後から2年目まではデータ分析業務に従事する。
3年目よりデータエンジニアとしてデータ基盤の構築を担当。現在はチームリーダーとしてマネジメント業務にも携わる。
 入社経緯
入社経緯
データの将来性とスタートアップの勢いに惹かれて
学生時代の専攻や得意だったことについて教えてください。
高校生の頃から数学が好きで、成績は英語のほうが良かったものの、進路は迷わず理系を選びました。立命館大学大学院の理工学研究科 数理科学コースに進学し、人工知能の内部ロジックが数学的に正しいかどうか、といった理論的な研究に取り組んでいました。いま仕事として携わっているデータエンジニアリングの領域と重なる部分も多く、偶然というより、運命のようなものを感じます。学生時代に培った論理的思考や数学的なアプローチは現在のプログラミングやデータ処理の業務に非常に役立っています。
就職活動ではどのような判断軸で業界や職種を選択されたのでしょうか?
比較的早いタイミングからエンジニア職を志望していました。きっかけは大学のサークル活動です。そのサークルはユニークで、コンピュータを使ってさまざまなジャンルで遊びながら学びを深めていこう、というものでした。サークル活動の同期がプログラミングに取り組んでおり、彼らとの会話の中で「いま、データ関連の分野が非常に注目されている」ということを知りました。数学を専攻していた私は、得意分野を活かせる領域ではないかと感じ、挑戦してみたいと思いました。
当時も現在も、データを扱う企業の多くは首都圏に集中しているため、就職先は東京を中心に考えながら地元の関西圏も視野に入れて検討しました。

DATUM STUDIOを選んだ理由について教えてください。
いくつか内定をいただいた中でも、最も面白そうだと感じたのがDATUM STUDIOでした。まず事業領域がデータ関連のITに特化していたこと。そして自主性が尊重される大学の研究室のような自由度の高い雰囲気と、型苦しさのないカジュアルでフラットな社風に惹かれました。当時は社員数が100名に満たない規模でまさに最初の成長フェーズだったことから、スタートアップらしいスピード感や変化のある環境で、多くの刺激を受けながら成長できるのではないかと思いました。
私が入社した2021年は、ちょうどコロナ禍でした。テックベンチャーは勢いのあるプレイヤーが多かった時期で、AIやLLM(大規模言語モデル)が注目されはじめたタイミングでした。DATUM STUDIOもその波に乗り、現在では200名近くにまで拡大していることは、この4年間の急成長ぶりを物語っているのではないでしょうか。
実際に入社してみての感想はいかがですか?
入社前に抱いていた印象とのギャップはなく、事前に感じたとおりの雰囲気でした。20代~30代のメンバーが中心ということもあり、カジュアルで話しやすくフラットな環境だと思います。
一方で、良い意味でのギャップとしては「高いスキルを持ったエンジニア」が在籍しているということです。中でも執行役員 兼 グループ会社のちゅらデータでCTOを務める菱沼さんは特に印象的な存在で、AIデータクラウドを提供するSnowflake社から卓越したSnowflakeの知識と実践力を備えデータの可能性を最大限に引き出すエキスパートに贈られる『Snowflake Data Superheroes』に4年連続で選出されるほど、そのスキルと活躍が業界内で高く評価されています。
DATUM STUDIOがSnowflakeをはじめとするデータ領域に特化したIT企業として認知されている背景には、菱沼さんを筆頭に技術面のみならずプロダクトの価値や優位性を社内外に発信するオピニオンリーダーとして活躍するメンバーが多く在籍していることも挙げられると思います。これは実際に入社して実感した当社の魅力であり、DATUM STUDIOの成長を加速させている強みでもあります。
 仕事内容
仕事内容

コンサルティングから領域を広げてエンジニアリングへ
現在の仕事内容について教えてください。
私が所属している部署はカスタマーアナリティクス部で、現在は大手コンビニエンスチェーンにおける物流システムの基盤を移管するプロジェクトに携わっています。ビジネスロジックは変えずに基盤システムをMySQLからSnowflakeに移行するという内容です。その中で設計・開発・検証を繰り返し行っています。
このプロジェクトにはすでに2年ほど携わっており、最近では開発フェーズのチームリーダーを務めています。主な業務は、開発メンバーからの質問対応やレビュー、PM(プロジェクトマネージャー)への報告などです。プロジェクトの初期段階では経験の浅さから周囲に迷惑かけることもありましたが、少しずつステップアップし、現在の役割を担えるようになりました。
キャリアのスタート時には、どんな仕事を担当されていたのですか?
配属先のカスタマーアナリティクス部は、もともとTableauなどのBIツールを用いたデータ分析や示唆出しといったコンサルティングに近い役割を担っている部署です。私自身入社1年目は、データ集計を中心とした案件に携わっていました。クライアントから依頼を受けて指定された形式でデータを抽出・集計し、提供するという業務です。他にも集計作業の中で気づいた点があればそれをフィードバックするなど、分析に近い業務も担当していました。
しかし入社2年目を迎える頃、自身のエンジニアリング知識が不足していることに対して危機感を覚えるようになりました。そこで上司に、エンジニアリング案件へのアサインを直訴したところ、現在の大手コンビニエンスチェーンのプロジェクトにアサインされることになりました。当時は5~6名規模のプロジェクトチームでしたが、現在では月あたり8名が稼働するまでに拡大し、リーダーやマネージャー、プロジェクト責任者など複数の役割が配置される体制に拡大しています。

エンジニアリング領域への挑戦を決意された背景を教えてください。
大きく二つあります。一つは、エンジニアの会話の内容を理解できるようになりたいと思った点です。エンジニアリングの知識がなければ指示されたことを実行するだけになってしまい、自分から主体的に提案することができません。周りの会話の内容を理解し議論を交わしながら仕事を進めるためには、エンジニアリングの知識は不可欠だと感じました。
もう一つは、エンジニアリングは「ものづくり」であり、最終的に「明確な成果物」としてアウトプットできる点です。データ分析の案件では、さまざまなデータを用いて仮説検証を行っても「結局、なぜその課題が発生しているのか」といった本質的な原因が特定できないこともあります。またデータ分析の領域のみだと、1ヶ月程の短期で案件が終わることも少なくありません。もちろん多くの学びはありましたが、より継続的に案件に関わり、成果が形として見える業務に携わりたいと思いました。
そこでコンサルティングとはまた別の切り口で社会に価値提供できるエンジニアリングの領域にチャレンジしたいと考え、業務領域の変更を希望しました。
提案は受け入れていただけたのでしょうか?
「前向きに検討します」と回答をいただき、すぐ具体的な調整に入りました。その結果、入社3年目からエンジニアとしてのキャリアをスタートさせることができました。データ分析の仕事ぶりと私のやる気を見ていただけたのだと思います。普段から確実なパフォーマンスを発揮していれば、自分の希望も通りやすいというのはどの会社にも共通していることかもしれませんが、特にDATUM STUDIOでは個々の努力や成果がしっかりと評価される文化と体制ができていると感じています。
 DATUM STUDIOでのやりがい
DATUM STUDIOでのやりがい

いかにして失敗から多くを学び、成長につなげていくか
初めての開発プロジェクトでは、どのような課題に直面しましたか?
やはり新しいプロダクトや技術、概念に思う存分触れられることです。私は、自分の知識量や経験値を増やすことにおもしろさを感じる性格なので、この点は非常に魅力を感じます。DATUM STUDIOはSnowflakeやdbt™といった、データクラウドを提供するさまざまなグローバル企業とパートナーシップを結んでいるため、日本ではまだ実例がないようなツールを使って事実検証をしたり、時にはリリース前の機能をいち早く体験させていただいたりと、貴重な体験ができるのです。そのおかげで、お客さまに最先端の技術を取り入れて提案することができ、実際非常に喜んでいただいています。
また、「超人」と言えるほどのものすごい技術知識を持ったメンバーと働けることも、DATUM STUDIOならではのメリットではないでしょうか。これは入社して数年経ったあとで気づいたことですが、普段社内で何気なく質問してやりとりしていた人が、実はデータ業界でトップクラスの知見を持っている方だった、ということがありました。こんなにすごい人と働いていたのかと驚いた経験が何度もあります。このような恵まれた環境で仕事ができていること自体が、自分自身のレベルアップに確実につながっていると思います。
リーダーとして仕事をする上で大切にされていることはありますか?
リーダーはメンバーから様々な質問を受けます。その際に心がけているのは、「自分が出した回答が、どう影響するか」を必ず想定することです。
間違った指示をしてしまえば、メンバーに無駄な仕事をさせてしまうだけでなく、プロジェクト全体に影響が及ぶ可能性もあります。回答を出す前には「本当にこれで大丈夫か」と一度立ち止まって確認するようにしています。自己判断が難しい場合は、ためらわずに上司やクライアントに確認を取ることも大切にしています。
こうした考え方が身についたのも、最初のプロジェクトでの失敗経験がきっかけです。「リスクがあることに気づかず進めることが一番怖い」という意識が強くなり、結果としてリスクマネジメントの視点を持てるようになりました。

仕事の中でどのような部分にやりがいを感じますか?
まず、純粋にコーディングそのものが楽しいです。たとえば、今携わっているプロジェクトでは、4月から会計システムの本番運用が始まり、それに伴いクライアントからのお問い合わせも増えています。対応する中で、保守調査やバグ修正のためにSQLでデータを調査することもあります。まるで論理パズルを解いているようで、非常に面白いですね。
またクライアントから「完成後は流通・小売業界や飲食チェーンなど、他業界のエンタープライズ企業にもこの物流システムを横展開していきたい」というお話をいただいています。自分が携わったシステムが、国内の物流を支える可能性が広がると考えると、大きな責任とやりがいを感じます。私たちの生活を支える重要な社会インフラである物流システムに私たちの技術が活かされていることは、社会的価値や仕事の意義を強く実感できます。
2年目まで主業務として携わっていたデータ集計もやりがいのある仕事でした。たとえば、グループ企業のアドテクノロジー事業の支援において、集計結果が「どのような広告を出すか」といった判断の基軸となり、ユーザーのクレジットカードの利用履歴をもとに顧客向けの施策を投じることになったこともありました。こうした業務は表には出にくいですが、クライアントの意思決定や戦略に大きな影響を与えるものです。それを実感できることこそがDATUM STUDIOで働く上での最大のやりがいであり、魅力だと思っています。

社会を動かすデータ活用の最前線に立つ
仕事における信念や姿勢を教えてください。
とてもシンプルですが、基本は「やるべきことをやりきること」です。それによって価値が生まれ信頼につながり、クライアントと当社の双方にとってWin-Winな関係が築けると考えています。
その際、言われたことをそのまま実行するだけでは不十分で、プラスアルファの価値をどう提供できるかが大切です。そのために意識しているのが、私の上司がよくおっしゃっている「A=B」という考え方です。Aはクライアント、Bは自社を表しており「両社の認識が一致している状態」が理想です。そこで必要となるのがコミュニケーションで、コミュニケーションが不足していると多くの場合で認識のズレが原因で問題が起こります。
この「A=B」の考え方は対クライアントだけでなく、マネージャーやメンバーとの認識合わせにも通じるものです。業務に関わる全ての人と認識がずれないようにすることを常に意識しています。
 DATUM STUDIOで描く未来
DATUM STUDIOで描く未来
卓越したエンジニアを目指して
今後どんな仕事にチャレンジしていきたいですか?
まずはいま任されているチームリーダーとしての役割を果たし、実力を高めていきたいです。その上での個人的な目標として、Snowflakeの案件に積極的に関わりたいと考えています。DATUM STUDIOにいる以上、SnowflakeをはじめとするDWHに精通することは自分自身のスキルアップにつながるだけでなく、会社にとっても大きな価値になると考えています。
最後に、どんな方にDATUM STUDIOの仲間に加わってほしいですか?
何より「データに興味がある」ことです。また、私たちのクライアントはエンタープライズ企業が中心となるため、社会的に影響力のあるプロジェクトに携わりたい方には非常にやりがいのある環境だと思います。
そして当社ではリモートワークを取り入れた柔軟な働き方ができるので、日々のコミュニケーションはWeb会議やSlackなどのテキストコミュニケーションが中心となります。そうした環境だからこそ、日々の何気ないやりとりや意思のすり合わせがとても重要です。技術はあとからでもキャッチアップできますし、今後は生成AIの活用によって補える領域もさらに広がっていくでしょう。だからこそ「人と人」とのつながりとコミュニケーションを大切にできる方に、ぜひ仲間になっていただきたいです。
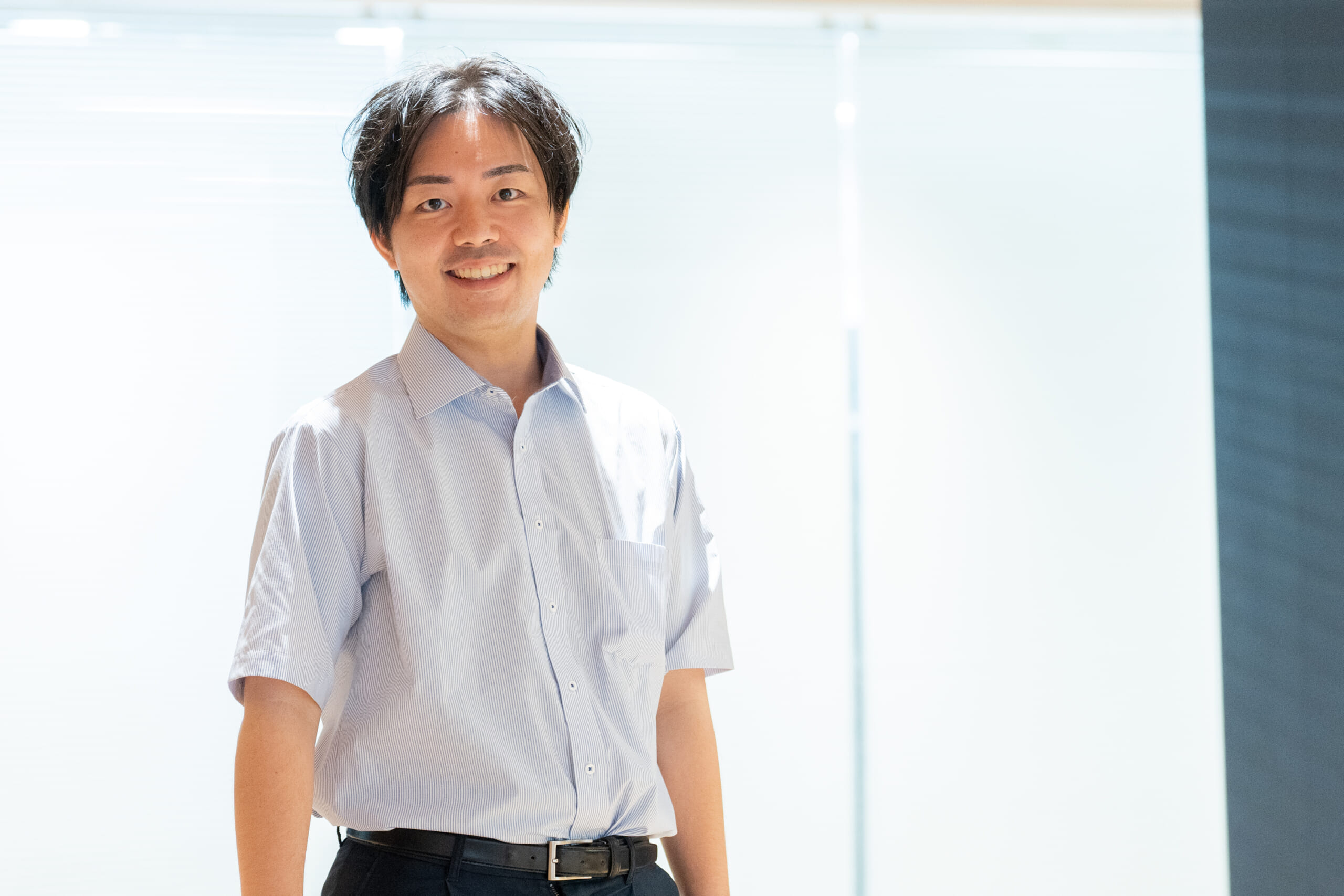
IN FUTURE