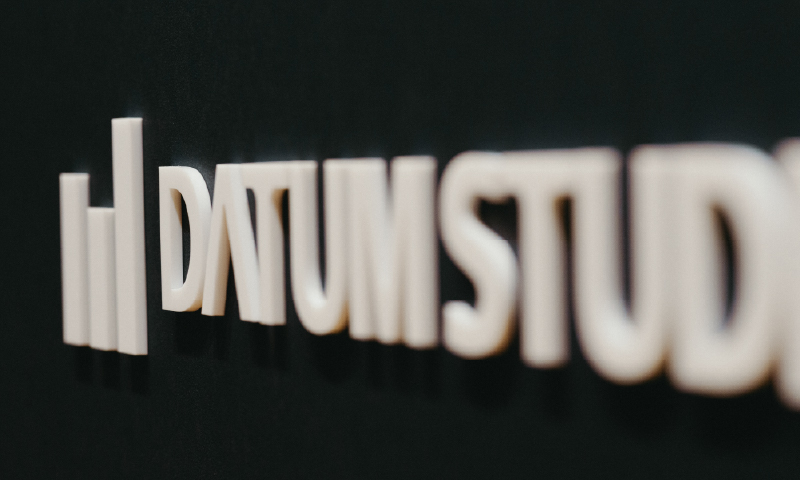magazine
ヒト・コトを知る
AI時代を切り拓く─技術とビジネスをつなぐコンサルタントのキャリア
コンサルティング本部
ストラテジー&コンサルティング部 部長
 略歴
略歴
大手総合コンサルティングファームを経て、現在はDATUM STUDIOのコンサルティング部門を率いるKaiさん。彼のキャリアの原点は、大学時代に探求した労働社会学にあります。社会課題への強い関心と、技術で何かを「つくる」ことへの憧れ。一見異なるベクトルに見える二つの軸をキャリアの中でどのように融合させてきたのでしょうか。大規模プロジェクトのリアルとAIの進化がもたらす課題、そしてDATUM STUDIOで描くビジョンについて伺いました。
 これまでのキャリア
これまでのキャリア

大手総合コンサルティングファームでキャリアのスタートを切る
まずはキャリアの原点についてお聞かせください。
大阪大学で労働社会学を専攻していました。その頃、アパレル業界での労働問題が問題視されており、アルバイトとして入社した企業を対象に、当事者の視点を踏まえて研究を進めました。
もともと幼少期から社会課題への関心が強く、中学時代には学校のプログラムでインドを訪れたり、高校時代には、地域で生活に困窮する方々を支援する活動に参加しました。こうした体験を重ねていく中で、社会の階層構造などに問題意識を抱くようになりました。
そこから大手コンサルティングファームに入社されたのは、どのような経緯があったのでしょうか。
周囲からは「まるで正反対の世界に進むのか」と驚かれましたね。
しかし研究を続ける中で、得た知見を直接活かせるキャリアは限られた選択肢しかないことに気づき「それなら自分の手で何かをつくる仕事がしたい」と考え、ゼロから挑戦できる分野としてITに着目。
SIerを中心に就職活動をしていたところ友人からコンサルティング会社の話を聞き、私の志望と比較的近い領域であることがわかりました。最終的に、大手コンサルティングファームから内定をいただき入社。配属先は金融グループで第1希望ではありませんでしたが、気持ちを切り替えてコンサルタントとしてのキャリアをスタートさせました。
コンサルティングファームではどのような業務を経験されたのでしょうか。
証券会社に常駐し、グローバルな金融規制に対応するデータベース整備のプロジェクトに従事しました。
私の役割は、ユーザーであるお客さまとエンジニアの間に立ち、要件を定義してロジックを組み立て、実装に向けた設計方針を策定すること。自らSQLを書いてデータを検証することもありましたが、今振り返っても当時扱っていた商品に対する計算ロジック以上に複雑なものはないと思うほど、難易度の高い仕事でした。
 入社経緯
入社経緯

専門性を高めつつ、それを応用できるフィールドを広げたい
そんな中、なぜ転職を意識されるようになったのでしょうか。
4年間にわたって金融規制に関するプロジェクトに深く携わり、その分野で高い専門性を身につけることができました。しかし一方で、キャリアの幅を広げたいという思いが強くなりました。これまで培った経験を土台に、一つの領域に留まらず、他の分野でも知識を活かし、多角的な視点から事業に貢献したいと考えるようになったのです。
これまでの経験を軸としながらも新たな領域に挑戦することで自身の成長を加速させたいと考え、転職を決意しました。
DATUM STUDIOとの出会いはどのようなきっかけだったのでしょうか。
きっかけは、コンサルティングファーム時代の上長の紹介です。
当時のDATUM STUDIOにはコンサルティング専門の部署がなく、現在のように分析基盤の構築からご支援するのではなく、お客さまからデータをお預かりし、分析した結果をアウトプットとして納品することが中心でした。
私が入社した2020年前後の頃は、「Snowflake」をはじめとするクラウドデータプラットフォームを提供している様々な企業と連携し、データ基盤構築からデータ利活用のご提案まで一気通貫でご支援するビジネスへ大きく事業をシフトさせていく過渡期。会社の仕組みが変わっていくダイナミックな変革を内部から目の当たりにできたのは、とても面白く貴重な経験でした。
 プロジェクトについて
プロジェクトについて

4年間で培った信頼と、プロジェクトマネージャーとしての挑戦
現在のプロジェクトマネージャーとしての業務についてお聞かせください。
ストラテジー&コンサルタント部のマネジメント業務も担当していますが、プロジェクトマネージャーとしての業務が大半です。
具体的には、大手商社の管理会計システム構築のPoC(概念実証)や大手小売企業のPOS分析システム構築など、複数のプロジェクトを同時に推進しています。私の主な役割は、お客さまの課題を解決するために、エンジニアと協力しながら最適なシステムや分析手法を検討し、プロジェクト全体を前に進めることです。
これまでのプロジェクトで、最も印象に残っているものは何でしょうか。
最も印象に残っているのは、約4年間にわたり継続している、大手食品関連企業様の経営ダッシュボードを構築したプロジェクトです。開始以来、3〜6ヶ月に一度のペースでリリースと機能改善を重ねてきました。
しかし、システム導入後の最初の3年間はお客さまの社内でなかなか利用者が増えないという課題がありました。既存の分析基盤と手法は長年にわたりお客さまの事業を支えてきた非常に完成度の高いもので、社内で深く浸透していたからです。そのため、私たちが構築した新しいシステムがそれを超える価値を提供できるとご理解いただくまでに、丁寧な検証と対話を積み重ねる必要がありました。
プロジェクト推進の体制が変わる局面もありましたが、私たちはデータをもとに粘り強く新システムの有効性を伝え続け、社内の皆さんとの信頼関係を築いていきました。そして今年、足掛け3年半にわたる取り組みがついに実を結び、本格移行のご決断をいただきました。お客さまとともに大きな課題を乗り越え、事業の未来に貢献できた瞬間はこの上ない喜びです。

プロジェクトを進める上で、特に難しさややりがいを感じる点は何ですか。
どのプロジェクトにも共通しますが、最もハードルが高いと感じるのは初期段階です。ゼロベースで要件を定義し、既存の環境に蓄積されたデータやロジックを紐解いていく作業は、高い専門性と経験が求められる重要な工程です。同時にこの過程はやりがいもあります。お客さまと対話を重ね、膨大なデータと向き合い続ける中で、最終的には「誰よりもその業務とデータに詳しくなる」ことが求められます。このレベルに達して初めて、お客さまから本当の意味での信頼を得られ、プロジェクトを円滑に進めることができます。
 DATUM STUDIOで描く未来
DATUM STUDIOで描く未来
AIの可能性と、テクノロジーとビジネスをつなぐコンサルタントの役割
DATUM STUDIOのコンサルタントとして働く魅力は何でしょうか。
最大の魅力は、日常生活では想像できないほどの規模とスピードでデータが動く様子を体感できることです。特にここ数ヶ月は、「Claude」に代表される生成AIの登場によって、そのスピードはさらに加速しています。エンジニアたちは新しい技術が登場すると瞬く間にその本質を見極め、実用化につなげていきます。こうした最先端の技術に常に触れることができる環境は、非常に刺激的です。
一方で、これはコンサルタントにとっての新たな課題にもなります。例えば、エンジニアが「今後はすべてのコードやドキュメントをAIで生成・管理するのがベストプラクティスだ」と提案した場合、技術的には合理的な発想でも、お客さまがその開発プロセスを即座に理解し、納得できるとは限りません。技術進化の圧倒的なスピードとビジネスの現場の間に生じるギャップを埋めることが、今後DATUM STUDIOのコンサルタントに求められる、きわめて重要な役割だと感じています。
今後に向けて、DATUM STUDIOでどのようなビジョンを描かれていますか。
個人としては、単にプロジェクトを成功させるだけでなく、より即応性の高い価値を提供できるようなソリューションを生み出せるよう成長したいと考えています。
組織としては、コンサルティング部門もメンバーが増え、新卒や若手社員も多くなってきました。だからこそ、私たちがこれまで培ってきたプロジェクトマネジメントのノウハウ、いわば暗黙知を形式知へと昇華させていくことが急務だと認識しています。
最後に、未来の仲間へメッセージをお願いします。
DATUM STUDIOは、まだまだ成長余地が大きい会社です。組織はフラットで、縦割りのしがらみはありません。そして、ここにはテクノロジーで社会を変えたいと奮闘する優秀なエンジニアやサイエンティストが集まっています。
しかし、ビジネスを進化させるためには技術だけではなく、ビジネス課題を解くコンサルティング力も欠かせません。
私たちはテクノロジーとビジネスを両輪で組み合わせることで、お客さまとともに新しい価値を生み出していきたいと考えています。
ぜひご自身の可能性を信じ、この刺激的な環境に恐れず飛び込んできてほしいと思います。

IN FUTURE